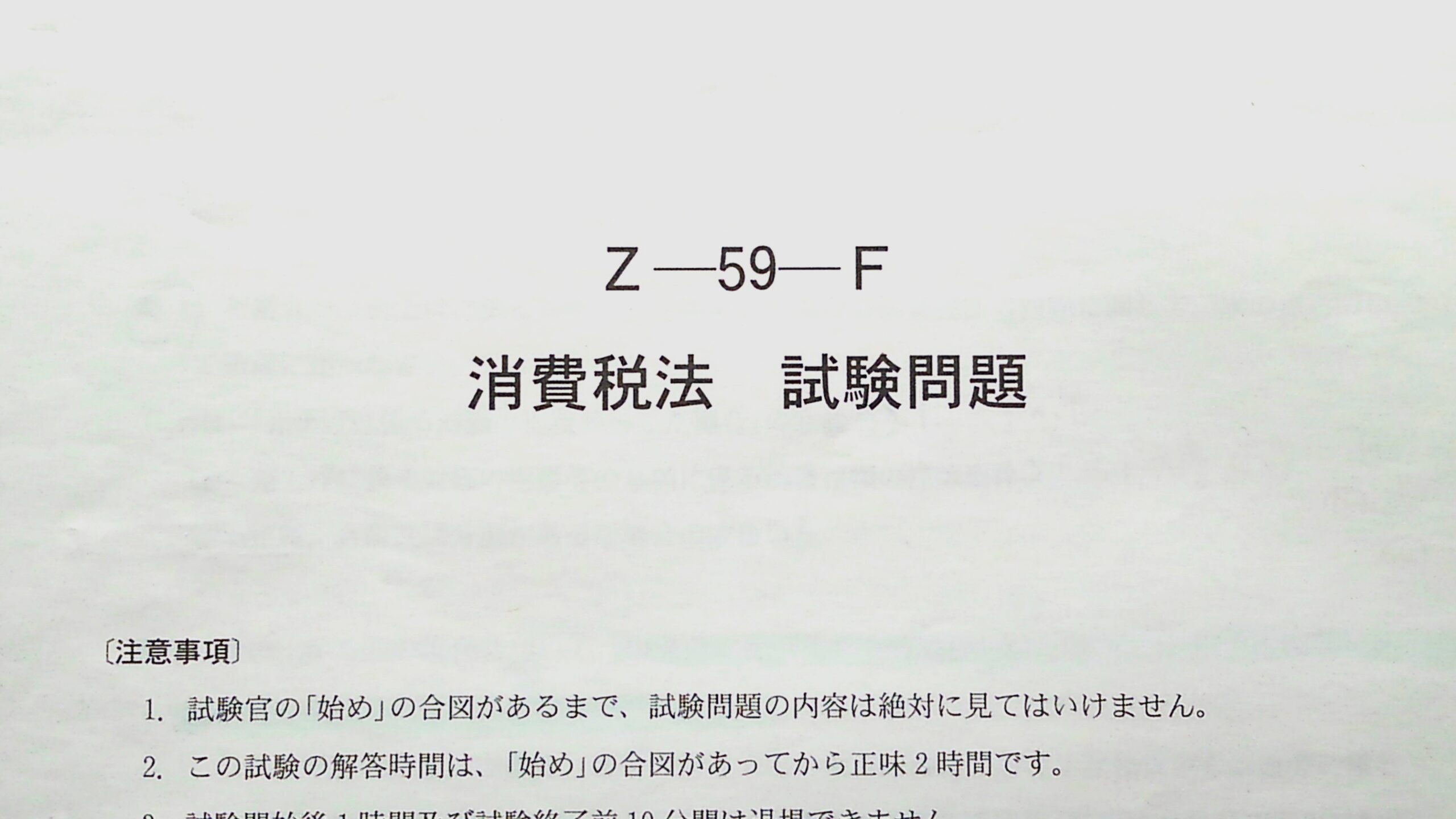税理士試験では計算の試験があるため、電卓はそれなりに大切になります。
しかし、そこまで電卓にこだわらなくても合格はできます。
ここでは、わたしが電卓に関して気にしていたことをかいています。
あまり電卓にこだわらなくても、合格はできる、とわかってもらえるとおもいます。
電卓も大原やTACで売っているものでいい
税理士試験で使用する電卓には、国税庁で決められたルールがあります。
問31 試験に使用できる計算機を教えてください。
(答) 計算機は、次の4つの条件の全てに該当する場合にのみ使用が認められます。
- 乾電池や、太陽電池で作動する電源内蔵式のものであること。試験場では、コンセントは使用できません。
- 演算機能のみを有するものであること。紙に記録する機能、音が出る機能、計算過程を遡って確認できる機能、プログラムの入力機能があるものは、その機能の使用のみならず、計算機全体が使用できません。(消費税の税込み、税抜き機能のみを有する電卓は使用可)
※ 「計算過程を遡って確認できる機能」とは、例えば、本人が入力した計算式や計算過程を記憶し、遡って画面上で計算式や計算過程を確認できる機能をいい、計算結果(答)のみを確認する機能(アンサーチェック(検算)機能(1回前の計算結果と答えを自動的に照合できる機能))はこれに該当しません。
国税庁 試験に使用できる文房具・計算機について 問31
- 数値を表示する部分がおおむね水平であるもの。表示窓が極端に横に倒れるものなどは使用できません。
- 外形寸法がおおむね26センチメ-トル×18センチメ-トルを超えないものであること。つまり、おおむねB5判の紙からはみ出ない大きさの計算機を使用してください。
基本的に、大原やTACで販売している機種であれば、自分で購入して国税庁の定める税理士試験用電卓に合ったものかを気にしなくていいという安心感があります。
両予備校の教材販売サイトを見ると、大原はカシオ、TACはシャープの取り扱いがありました。
これらが自身にしっくりくるかはわかりませんが、多くの受験生が使用していることから、とりあえず使ってみていいかと思います。
よほどこだわりがないのであれば、予備校推奨の電卓をそのまま使用して問題ないかと思います。
ちなみに、わたしはTACの受付で販売していたシャープのEL-G35を使用していました。
今は廃盤になっており、値段5000円程度で買ったものが1万円以上になっているなどプレミア化しています。
機能は最低限使えればいい
わたしが使っていた電卓の機能、あってよかった機能は下記のものです。
もっと便利な機能があるのかもしれませんが、これだけでも十分合格できました。
科目や講師によっては、最低限の機能の使い方も教えてくれます。
- M+ボタン
計算で数値を記憶させたいときに使用していました。
例えば、消費税の課税売上割合の小数を記憶させておくと、共通課税仕入れや一括比例配分方式の仕入れの計算で呼び出して使用できます。 - MRとMCは別のボタン
MRはM+で記憶させたものを呼び出すボタン、MCは記憶を消すボタンです。
安い電卓だとMRCボタンとして一緒になっており、これだと2回押すとメモリが消えてしまいます。
そのため、MRとMCが分かれているのは、誤操作を防げる点でもよかったです。 - 00ボタン
桁数の多い数字を入力するのに便利です。
1,000,000と入力するときに、「00」ボタンだと「1」→「00」3回でいけます。
「0」を6連打しなくていいので楽です。 - 12桁表示
12桁をフル活用する場面はあまりない気もしますが、消費税法の通算課税売上割合など、税法で大きな金額を扱う場合は12桁あったほうが安心でした。 - スタンドや液晶部分の傾斜
電卓のキーを打つ、液晶を見るときには斜めのほうが便利でした。
わたしは本体ごと斜めにできる機種だったため、液晶部分だけ傾斜できるものは受験では使用していませんが、傾斜があると便利です。
ノートパソコンをイメージするとわかりやすいでしょうか。 - サイレントキー(静音キー)
電卓のキー音は、本人が思う以上に周りに響いています。
安い電卓だとキーのカチャカチャ鳴る音が気になりますが、この機能があるものだと、その音が軽減されます。
電卓テクニックだけに固執しない
合格のためには、右利きの場合は電卓を左手5本指フル活用して打たないといけないイメージがあるかもしれません。
わたしは電卓をペンもったまま右手中指1本で打っていてもきちんと合格できましたので、電卓のスピードに自信がない方も安心していいです。
税理士試験は電卓テクニックを競う試験ではありません。
問題を読む読解力、そこから仕訳や税務判断をする判断力、集計方法なども重要になります。
そのため、計算のスピードを上げる場合は、電卓操作だけでなく、読解力などもあわせてスピードを上げるようにしましょう。
本試験には電卓の予備も持っていく
税理士試験中に電卓の故障などがあった場合、1年間を無駄にすることになってしまいます。
そのため、本試験には、念のため、同じ電卓をもう1台予備として机上に置いていました。
なお、電卓以外の筆記具や時計も予備を机上に置いていました。
電卓で周囲に迷惑をかけない
税理士試験に限らず会計系の試験勉強では電卓を使用することが多いです。
しかし、公共の図書館や一般の有料自習室で勉強する場合は、電卓の使用が禁止または制限されていることが多いです。
そのため、禁止されている場所では電卓を使用しないようにしましょう。
また、明確に禁止されていない場所でも、勉強やパソコンOKのカフェなら店員さんに念のため確認する、電車内では電卓を使用せず理論暗記など他の方法で勉強する、など周囲への配慮は忘れずに。
予備校の自習室など使用が許可されている場所でも、自分の電卓操作音が周囲に迷惑になっていると感じたときは、電卓の下にハンドタオルを敷くと、音を軽減することができます。
周囲への音が気になる場合は一度お試しください。
ただし、この方法は本試験では使えません。
まとめ
ここまで、予備校販売の電卓を機能にこだわらずに使って合格できたわたしの体験をかきました。
電卓をこだわらないと、つかいこなせないと、と悩んでいる方があまり気にせずに受験勉強できればとおもいます。