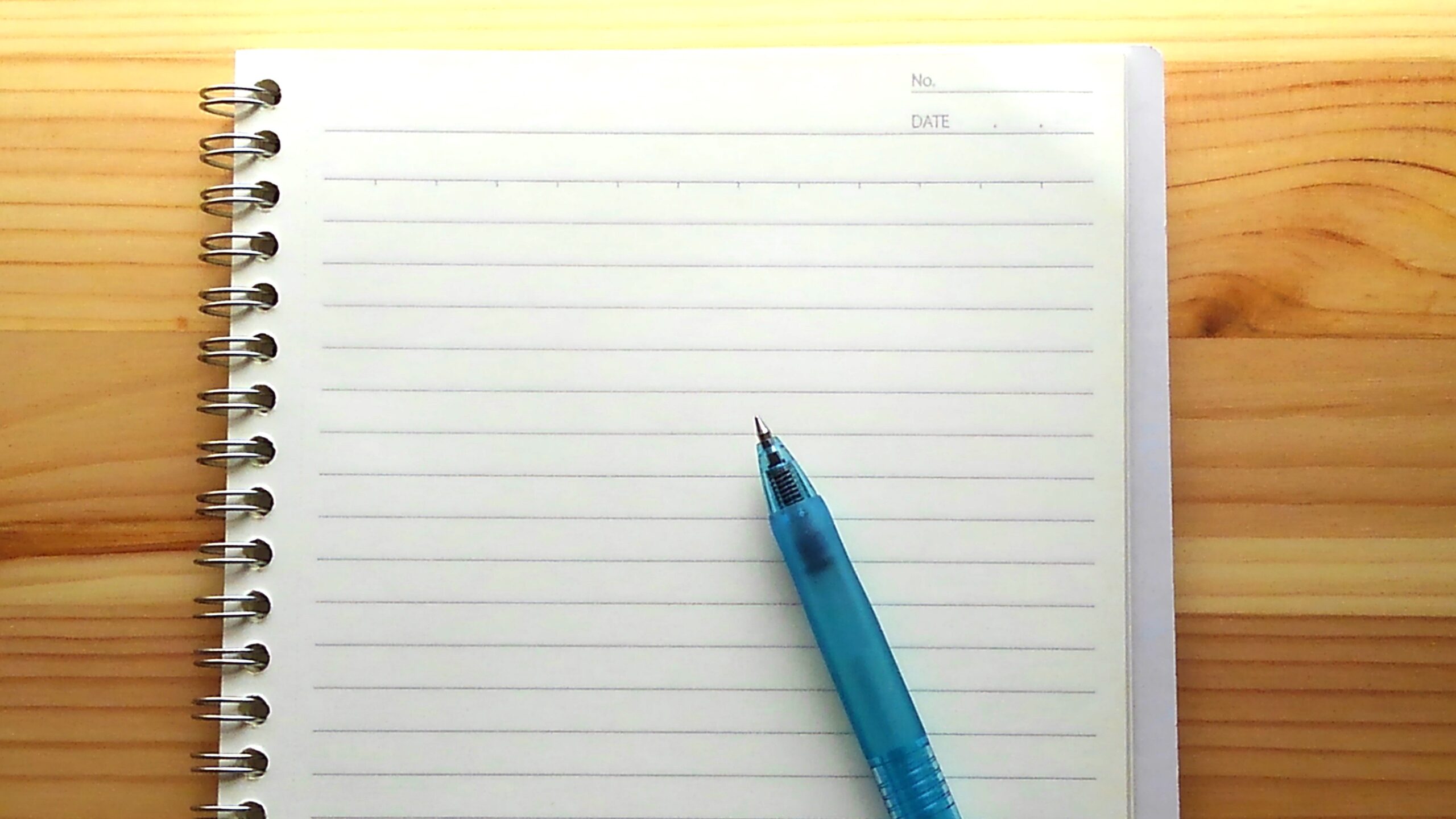モノが多すぎて管理ができない、断捨離・整理整頓は、家の中だけでなく、会社においても悩むところです。
会社では、昔から物流管理のシステムにより、モノを適正に管理する仕組みがありました。
今回は、病院の物流管理のしくみであるSPDについて説明しています。
SPD管理とは
SPDは「Supply Processing and Distribution」、直訳すると「供給・加工・流通」のことです。
病院で使う薬品や診療材料などをシステムで効率的に管理する仕組みのことをいいます。
ざっくり言うと、薬品や診療材料に管理用のバーコードをつけておき、購入や使用の際はバーコードをシステムに読ませて、モノを管理します。
下記のような流れになります。
- 購入時にバーコードをつける
- バーコードをシステムに読ませて購入と登録する
- 使用時にバーコードを外して回収箱に入れる
- 回収箱に入ったバーコードをシステムに読ませて自動発注する
モノの管理や搬入作業は、病院内の専門部署または外部業者が行います。
たいていは、病院が関連会社を作り、そこに委託することが多いです。
モノの流れが「仕入れ先→SPD会社→病院」の順に流れる点は、病院のSPDの仕組みでは共通しています。
主に管理と運用にあたっては、次の2点が特に問題になりますが、細かい点を挙げていくといろいろな仕組みがあります。
- モノを置く倉庫をSPD会社か病院のどちらで保管するか
SPD会社内に倉庫を用意する(病院が使った分だけ補充にもっていく)
病院内に倉庫を用意する - 在庫はだれのものか
仕入れた時点で病院の在庫とする(購入)
バーコードを外して使うまではSPD業者の在庫とする(預託)
SPD管理のメリット
SPDシステムでの管理のメリットは次の通りです。
管理業務の効率化ができる
バーコードで管理することで、モノの消費量と在庫量をリアルタイムに把握できます。
たとえば、ある部署で5個の定数で管理していた材料が毎月3個しか使われていないことがわかります。
これだと、2個が過剰在庫になっているので、定数を3個に減らせば、適正に管理ができる、といった判断ができるようになります。
また、毎月の消費量を把握することで、大量購入しているモノであれば、「たくさん買っているので安くしてほしい」と価格交渉の余地ができます。
年末年始など、仕入れ先が休みの時は、過去の使用実績から定数外で臨時発注して備える、といったこともできます。
医療事務業務の効率化ができる
病院での診療行為は「○○をしたら××円」と国が決めています。
医療事務は、カルテの内容などから、上記の情報を読み取って、保険の診療報酬の計算を行います。
手術などの場合、身体の部位や手術の方法に加えて、使った材料も計算の対象になります。
その際に、バーコードのシールを手術のレポート・伝票に貼り付けておくことで、手術で使用した材料の把握・計算が効率的に行えます。
これにより、収益の柱である診療報酬の計上漏れを防ぐことができます。
預託形式の場合、未使用物品は返却できる
預託形式の場合、バーコードを外して使用するまでは病院の在庫になりません。
治療方針の変更や期限切れ間近などで使用しない場合は、返却ができます。
病院のモノでないため、返却しても会計処理は不要です。
SPD管理のデメリット
SPDでもミスがある
管理の仕組みがあっても、人の手で作業する以上は、ミスはあります。
たとえば、バーコードの読み取り忘れあると、購入や消費・発注が適切に行えなくなります。
また、管理用のバーコードを1枚紛失すると、対応するモノの在庫が1つ少ないまま業務を行うことになります。
再発行した後でバーコードが見つかると、今度は二重に運用ということもあります。
そのため、定期的なモノやバーコードの管理は重要になります。
預託返品トラブルの可能性がある
病院にとっては、お金はかからず返品できるのが預託形式のメリットです。
そのため、気軽に頼んだけど使わずに返品ということもあります。
しかし、SPD業者にとっては、返品されたものを仕入れ先に返品する、他の納入先を探すといった問題が生じます。
やむを得ない返品もありますが、使うものと定数を決めることが大切です。
まとめ
病院での物流管理の仕組みであるSPDについて紹介しました。
効率化する仕組みを利用すれば、モノの管理は楽になります。
ただし、仕組みを作ってもミスは起こるため、結局は適切に運用することが重要になります。