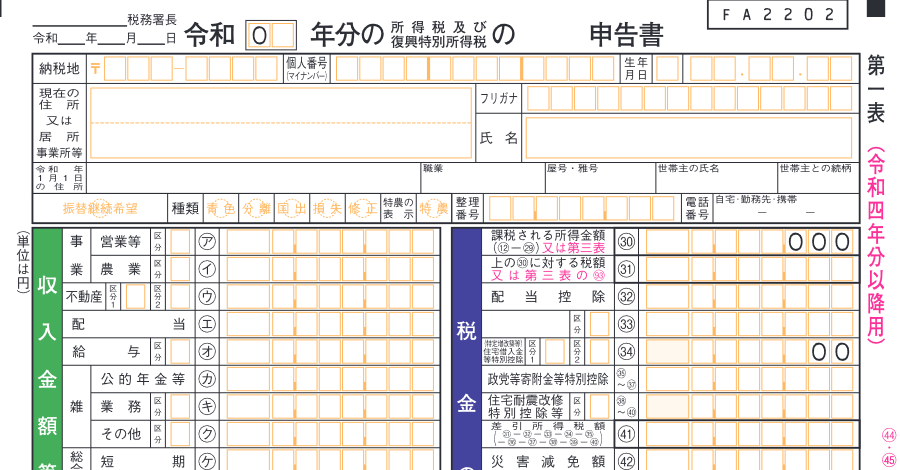税理士という仕事柄、様々な方の会計ソフトのデータや紙での会計帳簿を見る機会があります。
その際、「摘要」(ソフトによっては「備考」)の記載がないケースを多く見かけます。
会計ソフトの摘要とは、その取引の内容を説明するために重要な役目があります。
今回は、摘要を書かないデメリットと摘要の書き方について書いています。
書かないデメリットと原因
摘要を書かないデメリットは、後から見たときに取引内容がわからないことです。
たとえば、クリニックを開業している医師が、○○書店から7月20日に5,000円分の本を買ってその代金を銀行口座から振り込んだ場合は、次のように処理します。
7/20 借方 新聞図書費 貸方 普通預金 5,000円
この記載だけで何か問題になるのかわからない方もいると思います。
しかし、この記載だけでは、後から見ても新聞図書費の内容がわからないという問題があります。
「書かなくてもすべて覚えているから問題ない」という方も中にいますが、確定申告が終わった数年後まですべて覚えていることは難しいでしょう。
税理士として会計ソフトのデータを見たときに、摘要に何も書かれていなければ、それが正しい内容かどうか確認することができません。
クリニックで本を買う場合、医師やスタッフの勉強のための専門書籍を買う場合があります。
こちらは領収証などで書籍名がある場合は、勉強用のため必要経費だと明らかにわかります。
その一方、患者さんの待合室に置くために、専門書籍ではない雑誌や漫画などを買う場合があります。
プライベートでも雑誌や漫画を買うこともあるため、雑誌や漫画の領収証があったとしても、プライベートの費用をクリニックの経費にしようとしてるのでは?と疑われてしまいます。
そこで、次のように摘要を書くことで、きちんと事業のための必要経費だとわかるように処理します。
7/20 借方 新聞図書費 貸方 普通預金 5,000円
(摘要) ○○書店 クリニック待合室用雑誌代
このように摘要を残すことで、後から見ても事業用だと明らかにできます。
また、領収証を見ても雑誌の名前だと、プライベート用ではないかと疑われてしまいますが、きちんと「クリニック待合室用」と残すことで、その疑いを解消することもできます。
(待合室に雑誌が置かれた実績があることが前提です。プライベート用にもかかわらず事業用として摘要を書いて経費計上することは認められません)
摘要を書かないケースを多く見かける理由としては、次の2点があると思います。
1点目は、簿記や経理の勉強では、左右に何の科目と金額が来るかといった仕訳の仕方は教えても、摘要の書き方までは教えないからだと思います。
わたしも摘要を書くことについては、簿記の勉強では習わず、実際に会計事務所や経理職で教わりました。
2点目は、クラウド会計ソフトの同期を使って通帳やクレジットカードのデータを記録した際に、同期された情報のまま登録をしてしまうケースがあるからです。
同期機能は便利で、手入力をしなくて済むメリットがあり、通帳やカードの明細の情報は摘要にそのまま記載してくれますが、詳細は書いてくれません。
また、都度詳細を加筆するか、毎回同じ内容であれば自動登録のルールで詳細を加筆する設定をします。
同期できない場合は、取り込み前のエクセルのコピペや会計ソフトの取引のコピーを使うことで少し効率を上げることができます。
摘要の書き方
それでは、摘要をどのように書けばいいのか、は悩むところです。
所得税や法人税でも明確な書き方は決まっていません。
参考になるのは、消費税法で決められた帳簿の記載事項についてです。
下記の国税庁のタックスアンサーに帳簿への記載事項が書かれています。
仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。
(1)課税仕入れの場合
イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
言い換えると、「一般的な経費の支払いの場合、相手の名前と年月日と内容と金額を書きましょう」ということです。
最初に例で挙げた雑誌の支払いに当てはめると、次のようになります。
「相手の名前」=「○○書店」
「年月日」=「7月20日」
「内容」=「新聞図書費」と「クリニック待合室用雑誌代」
「金額」=「5,000円」
日付と金額と内容の半分は仕訳で記載済みのため、摘要に書かないといけないのは、相手の名前と科目ではわからない内容の2点です。
「○○書店 クリニック待合室用雑誌代」のように相手の名前と科目だけではわからない内容を書きましょう。
科目だけではわからない内容は、単に「雑誌代」と書いてもいいですが、目的や用途(今回だと「クリニック待合室用」)・具体的な雑誌名など詳細を書くことで、後で内容の確認や必要経費であることを明らかにできます。
ほかの科目の場合は、例えば次のように書くとわかりやすいと思います。
・会議費
○○カフェ 飲料代 Aさんと月次打ち合わせ(代金各自負担)
※飲食代が割り勘で1名分しか領収証にない場合は、摘要に打合せ相手や内容、割り勘の旨も残すようにします。
・交際費
和菓子屋〇〇 御菓子代(B社訪問時手土産)
レストラン〇〇 飲食代4名 B社C部長、D課長ほか1名 プロジェクト慰労会
※法人の場合は、交際費は経費精算書類だけでなく、摘要にも相手や飲食人数と目的を記載しておくと1人当たりの飲食代の金額の確認を会計ソフトだけで完結できます。
・通信費
○○モバイル 当直当番用スマホ代 12月分
※スマホなど当月分の料金が翌月以降に口座振替される場合は、少なくとも年をまたぐ分(法人は決算期をまたぐ分)は何月分か書くことで、決算時の未払計上もれなどのミスを防ぐことができます。
・旅費交通費
JR東海 新幹線代(東京~大阪往復) E社訪問
※プライベートの旅行と疑われないよう、業務上の目的も書いています。
・賃借料
〇〇リース CT装置リース料 49回目(全60回払)
〇〇リース MRI装置リース料 7月分(契約期間 2025年7月~2030年6月)
※長期間契約や分割払いの場合は、期間や回数も書くことで契約完了後の過払いの防止や次回の契約更新のタイミングも管理できます。
このほか、経費精算が必要な職員が複数いる場合は精算した職員の名前や経費精算書の管理情報を書く、会社の稟議や承認を経ての支出の場合はその稟議書の日付や番号を書くなど、摘要にできるだけ情報を残すことで、社内管理に活用することができます。
過去、法人の経理をしていた時に、経営陣から「××案件の経費」「Fさんが申請した経費」などの情報を一覧で見たいと要望がありました。
会計ソフトには検索機能があり、さらに今は領収証などのデータも会計ソフトに添付ができます。
そのため、日頃から会計ソフトの摘要で管理しておくことで、こういった要望にもすぐに対応できます。
おわりに
会計ソフトで摘要を書かないデメリットと書き方について書きました。
日頃の処理ではおろそかになる部分ですが、きちんと書くことで、決算や申告の際の内容のチェックやその後の管理にも活用できます。