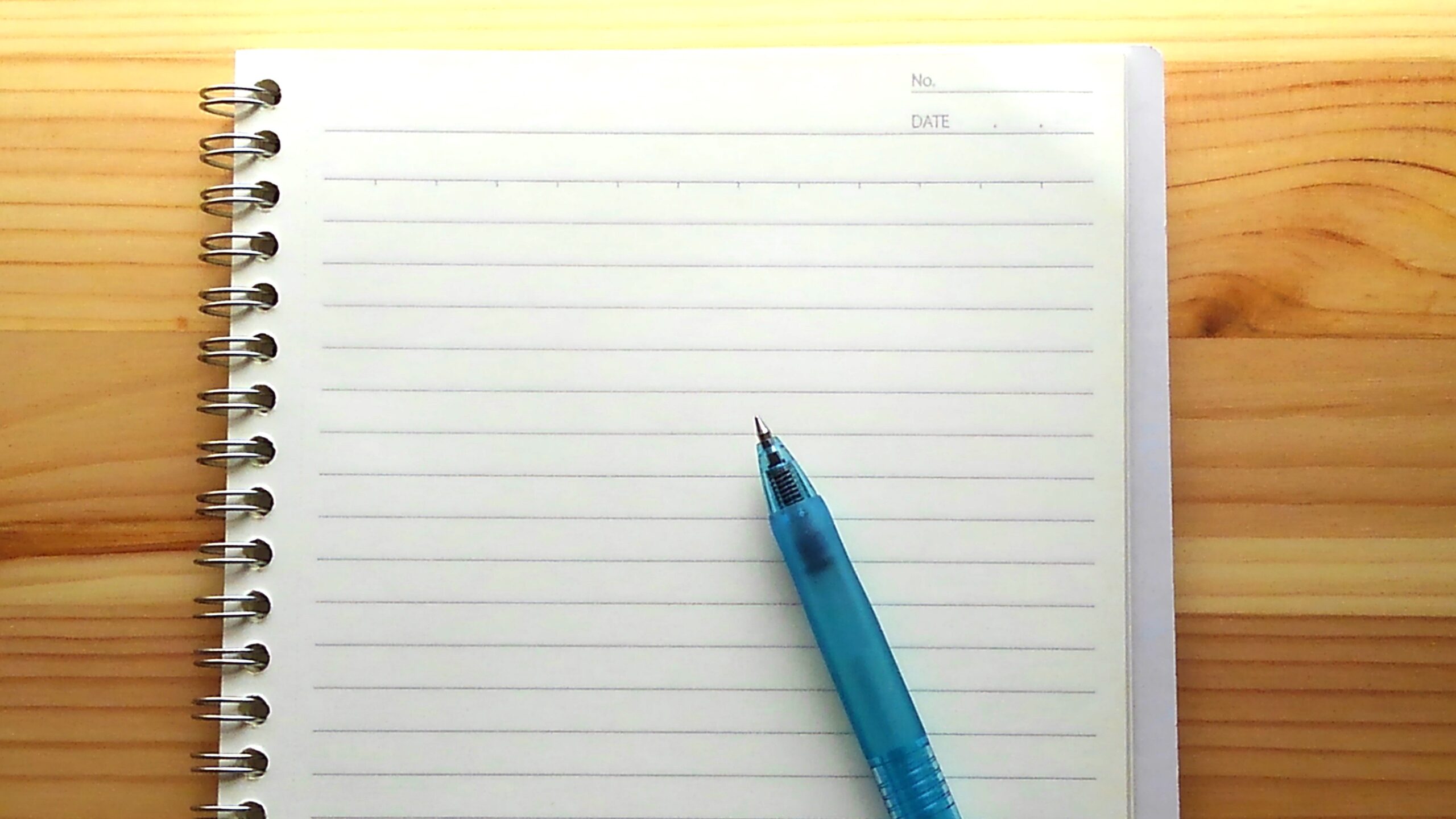同じ経営者が複数の支店(店舗やクリニックなど)を運営する際に、同じ業種であっても、時間がたつにつれてだんだんと支店ごとに仕事の進め方などが異なっていく場合があります。
これを支店ごとの個性として認められる面もありますが、あまりに個性として認めすぎてしまうと、問題も発生します。
特に、経理や給与計算その他総務などの事務系業務を支店ごとに異なる手続きになってしまう場合は、運営・管理しきれなくなるという問題が起こります。
今回は、複数の支店で同じ事務系業務をするときの注意点について書いています。
事務のルールを統一する
事務系業務については、社内でルールを統一し、それを運用することが重要になります。
そのためには、本部や本店総務など、支店をまとめるための部署の設置が必要です。
この部署で就業規則や経費精算といった、会社全体の経理・人事・総務などの書式や手続きの流れなどの社内ルールなどをきちんと作成します。
そして、その社内ルールに即して日々の業務を進めるようにします。
社内ルールを統一することで、次のメリットがあります。
- 経営者から見ると、会社として各支店の経営成績の比較や管理を効率化できる
- 本部の職員から見ると、どの支店でも手続きが同じため、本部内での情報共有や業務を効率的に行うことができる
- 各支店の職員から見ると、別の支店に異動したとしても同じルールなのでスムーズに新しい支店になじむことができる
社内ルールが統一されていない場合は、次のデメリットがあります。
- 経営者から見ると、各支店でルールや条件が異なるため、支店ごとの経営成績の分析や比較をきちんと行えなくなる
- 本部の職員から見ると、支店ごとに手続きが異なるため、支店ごとの細かいローカルルールを覚える手間がかかり、情報共有が行われづらくなる
- 各支店の職員から見ると、異動した支店ごとにルールが異なるため、新しい支店での業務に負荷がかかりやすい
また、社内ルールとして統一した運用をするためには、全員に同じ指示をする必要があります。
社内ルールを長い期間運用するうちに、個別の事情や特例など出てくることがあります。
そういうときは、きちんと組織全体で運用方法を変更し、改めて変更されたルールを周知する必要があります。
システムを導入する
統一した社内ルールを運用するためには、システムを導入することも1つの選択肢です。
アナログな運用だけの場合、本部や経営者からの指示が各支店の職員に届かない、一部の支店だけ違う手続き(古い書式のまま)などの問題が起こります。
たとえば、出勤や退勤の時刻管理にタイムカードを設置するのもシステムの1つです。
客観的に退勤時刻を示すものがないと、時間外労働や残業代に関するトラブルのもとになります。
ただし、アナログなタイムカードの場合は、出勤していないのに他の人がタイムカードに打刻する、間違えて他の人のカードに打刻する、といった不正やミスが発生します。
また、アナログなタイムカードや残業申請の用紙から残業時間を計算する作業は、毎月手間がかかるうえ、計算ミスの原因にもなります。
今は、パソコンやスマホで職員番号とパスワードで不正打刻を防いで、出勤時刻・退勤時刻や残業内容などを入力することで、自動的に勤怠管理や給与計算と連動できるシステムもあります。
きちんとパソコンと連動できるシステムであれば、残業内容の記載漏れや打刻ミスなどはエラーで表示されるため、職員自ら修正することができます。
そして、システムで自動で残業時間や有給休暇消化などを処理・管理してくれるため、本部で毎月給与計算をする際にも手計算しなくてすむなどの効率化ができ、業務負担が軽くなります。
経費精算や慶弔申請などの福利厚生、その他の社内手続きについても、手続きのためのシステムを導入する、それが難しいのであれば社内LANなどで統一した書式を常備する、など統一したしくみを少しでも導入することが大切です。
このしくみにすることで、社内ルールの変更があった場合にシステムを変更する・システム経由で連絡するだけで、各職員への情報周知が早く正確になります。
このしくみ作りができていないと、特定の支店だけ不備のある古い書式を使い続けている・ルールが古いまま運用されている、といった問題が発生します。
このように、会社内で統一したルールを運用するために、デジタルなシステムを導入することで、公正な組織の運営と業務の効率化を行うことができます。
おわりに
複数の支店で同じ事務系業務をするときの注意点について書きました。
統一した社内ルールをしっかり作ることと、システムとして導入することで、支店が増えても統一したルールに基づいた運用がしやすいかと思います。
あと、わたしが事務職を経験した立場だからこそ言えるのですが、事務職員を組織の中で下に見ない(位置づけない)ことが重要です。
組織の中の事務職や本部職員は、現場の職員と違って直接お金を生む仕事ではありません。
そのためか、経営者も現場の職員を事務職員を下に位置づけて見ている人が意外と多いです。
このような組織の場合、上から各現場に同じように指示を下したとしても、現場がきちんとしていない場合、事務職がそのきちんとしていない状況をフォローすることになります。
(ゴミ箱にゴミを捨てる感覚で事務手続きの不備を押し付けてくる人は意外といました)
書類の不備の修正、支店ごとの不統一な書式の整理など、本来組織のルールやシステムがきちんとしていれば発生しない無駄な業務を、事務職が受け入れないといけないという不合理が起こります。
その無駄を本来の事務系業務(経理など)にまわすことで、無駄や経費を削減して組織の利益に貢献することになります。
したがって、ルール作りやシステム化とともに、組織としての不合理や無駄を事務職に押し付けていないか、事務職の立ち位置についても検討する必要があるのではないでしょうか。